- HOME>
- 肝機能障害の症状・進行リスク・数値の見方・判断基準
肝機能障害の症状と進行リスク
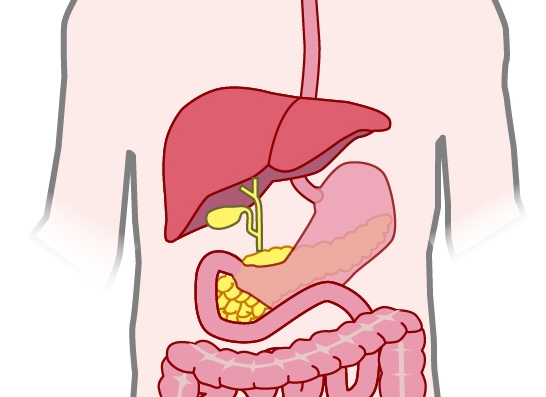
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、障害があっても初期にはほとんど症状が現れません。
しかし、注意深く観察すれば、早い段階で異変を察知できるサインがあります。
以下では、初期に気づきたい肝臓の症状や進行時の変化、そして放置することの危険性について詳しく解説します。
見逃さないで!肝機能障害の初期サイン
初期の肝機能障害は、自覚症状があっても非常にあいまいで、疲労やストレスと勘違いされがちです。
いとせクリニックでも「何となく体調がすぐれない」と来院され、検査で肝機能異常が判明するケースは少なくありません。
全身のだるさや疲れやすさ
十分な睡眠を取っても疲れが抜けない、体が重く感じるなどの状態は、肝機能低下によりエネルギー代謝が滞っているサインかもしれません。
肝臓が疲弊すると疲労物質の分解がうまくできず、慢性的なだるさにつながります。
風邪や過労と間違えて放置すると、症状が進む恐れがあります。
食欲不振や吐き気
胃腸の不調と勘違いしやすいですが、肝臓機能の低下が原因で消化吸収がスムーズに行われず、結果として食欲減退や吐き気が生じる場合があります。
お腹の張り
内臓脂肪や肝臓の炎症による腫れが、お腹の圧迫感や張りを感じさせることがあります。
アルコール性脂肪肝の初期に多く見られます。
症状が進行してから現れるサイン
病気がある程度進行すると、外見や生活に影響する症状が出やすくなります。
この段階では肝臓へのダメージが進んでいる可能性が高く、早急な受診が必要です。
黄疸
黄疸はビリルビンという色素が血液中に増えることで起こります。
皮膚や白目が黄色く変色するため見た目にも分かりやすい特徴の一つです。
足のむくみ
肝臓でのたんぱく質合成が低下し、血液中のアルブミンが不足することで、特に下半身にむくみが出やすくなります。
尿の色が濃くなる
通常よりも濃い褐色になるのは、ビリルビンの排泄異常によるものです。
皮膚のかゆみ
胆汁成分が皮膚に沈着することで、全身に強いかゆみを感じる場合があります。
手掌紅斑やクモ状血管腫
手のひらが異常に赤くなったり、胸や肩にクモの巣のような血管が浮き出たりすることがあります。
こうした異常は、肝機能障害が肝硬変へ進行しているサインです。
なぜ早期発見が重要なのか
肝機能障害は症状が出にくく、気づいた時には進行していることが多い病気です。早期発見が重要な理由は次の通りです。
重症化を防ぐため
肝機能障害や肝臓からの不調サインを放置すると、慢性肝炎→肝硬変→肝がんへと進行するリスクが高まります。
脂肪肝の一部は最終的に肝硬変や肝がんの原因になり得ます。
アルコール性肝障害も飲酒習慣を続ければ確実に悪化してしまうため注意が必要です。
改善・回復の可能性を高めるため
早期であれば、生活習慣の改善や薬物療法で機能が回復する可能性があります。
例えば、脂肪肝は禁酒・節酒、バランスの取れた食事、定期的な運動で正常に戻せるケースが多いです。
ウイルス性肝炎に関しては、最新の抗ウイルス薬でウイルスの排除や活動抑制が可能になっています。
放置した場合に起こりうる進行リスク
肝臓は、解毒・代謝・栄養管理など生命維持に欠かせない働きをしています。
この機能が損なわれると全身への影響は計り知れません。
初期症状が少ないため、気づかぬうちに病状が悪化しやすいのが特徴です。
慢性肝炎
慢性肝炎はその名前の通り、肝臓に炎症が長く続く状態です。
原因はウイルス(B型・C型肝炎)、自己免疫、薬剤、アルコールなどさまざまですが、進行はゆっくりで自覚症状がほとんどありません。
健康診断や血液検査で肝機能異常が見つかり、初めて気づくことが多いです。
この段階では、炎症を抑える治療を始めれば進行を止められる可能性があります。
しかし放置すると、肝細胞が徐々に壊れて健康な組織が失われ、元の状態には戻らなくなります。
肝硬変
慢性肝炎がさらに進むと、壊れた肝細胞が硬い瘢痕(はんこん)組織に置き換わります。
肝臓はしなやかで柔らかい臓器ですが、この瘢痕組織によってゴツゴツと硬くなり、血流や働きが著しく悪化します。
症状としては、腹に水がたまる「腹水」、食道や胃の静脈が破れて起こる「吐血」、体内に有害物質がたまり意識障害を引き起こす「肝性脳症」などがあります。
ここまで進むと肝臓の機能を取り戻すことはほぼできず、治療は進行を抑えて合併症を防ぐことが中心になります。
肝臓がん
肝臓がんは、肝障害の最終段階ともいえる状態です。
長期の炎症や硬変によって傷ついた肝細胞が異常に増殖し、腫瘍を作ります。
早期で発見できれば手術やラジオ波焼灼療法、抗がん剤などで改善が見込めますが、症状が出る頃には進行していることも多く、治療の選択肢が限られます。
特に肝硬変を持つ人は肝臓がんの発症リスクが高いため、定期的な超音波検査や血液検査での監視が欠かせません。
肝機能障害の数値の見方と判断基準
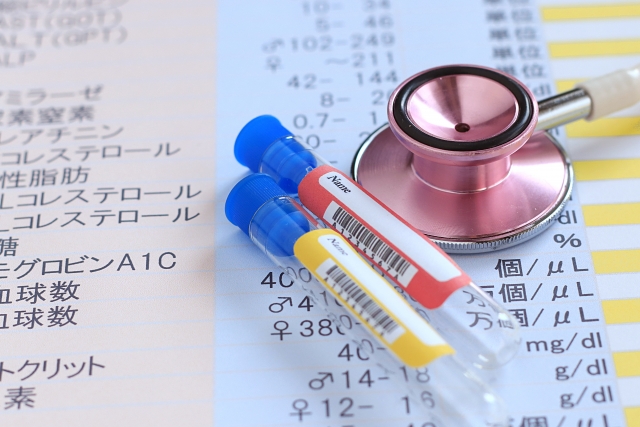
肝機能障害とは、肝臓の働きが何らかの原因で低下している状態のことを指します。
肝臓は体内の毒素を分解し、栄養の代謝や血液の生成など、生命維持に欠かせない役割を持つ臓器ですが、ウイルス感染や脂肪の蓄積、過度な飲酒などにより肝細胞が傷つくと、肝機能障害が起こります。
多くの場合、初期は自覚症状がないため健康診断の血液検査で異常が発見されることが多いのが特徴です。
健康診断での肝機能検査の重要性
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、障害があってもすぐには症状が現れません。
そのため、むくみや黄疸など明らかな症状が出たときには病気がかなり進行していることが多いです。
そこで定期的な健康診断での血液検査は、肝機能の異常を早期に発見し、適切な対処を行う上で非常に重要となります。
年齢とともに肝臓への負担は知らず知らず増えているため、毎年の検査を欠かさないようにしましょう。
AST(GOT)とALT(GPT)の意味と違い
ASTとALTは肝臓の状態を示す代表的な酵素です。
どちらも肝細胞に含まれる酵素で、細胞が壊れると血液中に流れ出し数値が上昇します。
ASTの特徴
ASTは肝臓だけでなく筋肉や心臓、赤血球などにも存在しているため、上昇しても肝臓障害とは限りません。
運動後や筋肉痛でも高くなることがあります。肝臓の急性炎症時に特に上昇します。
ALTの特徴
ALTは主に肝臓に存在し、肝細胞の障害に敏感に反応します。
ALTが高いと肝臓特有のダメージが疑われます。
ASTとALTの比率からわかること
一般的にALTの方が高い場合は慢性肝炎や脂肪肝の可能性が高く、ASTの方が高い場合は急性肝炎やアルコール性肝障害の急激な悪化が疑われます。
これらの数値のバランスを見ることで、病状の種類や進行度を推測できます。
γ-GTPの役割と注意点
γ-GTPは主に肝臓と胆道系で作られる酵素で、アルコールの影響を非常に受けやすい指標です。
普段から飲酒量が多いと上昇しやすく、持続的な高値は肝臓や胆管の障害を示唆します。
胆管結石や胆管がんでも数値が上がり、胆道系疾患のスクリーニングに使われます。
飲酒を控え一定期間経っても数値が下がらなければ、肝臓疾患の疑いが強まります。
また、近年では非アルコール性脂肪肝炎(NASH)でもγ-GTPの上昇が報告されており、アルコールに関係なく肝炎の指標として重要視されています。
ALPとは何か?胆道の状態を映す指標
ALPは肝臓や骨、腎臓など複数の臓器で作られる酵素ですが、肝臓から胆汁の流れが妨げられると血液中に増加します。
胆管の閉塞や胆石、胆道がんなど胆道系の異常を推測する上で欠かせない検査です。
ALP単独での診断は難しいため、ASTやALT、γ-GTPなどと組み合わせて評価し、肝障害の原因や位置を判断します。
骨疾患や骨の成長期でも上昇するため、患者の年齢や背景も考慮する必要があります。
総ビリルビン値の意味とその重要性
ビリルビンは赤血球の分解産物で、肝臓で処理され胆汁と一緒に体外に排出されます。
肝臓や胆道の機能障害があると処理が追いつかず血中ビリルビンが増加し、皮膚や白目が黄色くなる黄疸を引き起こします。
総ビリルビンが高い場合は胆道閉塞や肝硬変、肝臓がんなど重大な疾患が隠れていることがあり、早急な精密検査が求められます。
生まれつきビリルビンが高い体質もあるため、経過観察や追加検査で区別が必要です。
肝機能異常の際に行う精密検査とは
血液検査で異常が見つかった場合、さらなる詳細検査が必要です。
腹部超音波検査
肝臓の大きさ、脂肪の蓄積、腫瘍の有無、血管の形状や線維化の程度などを非侵襲的に評価できる検査です。
短時間で患者の負担が少ないため初期検査に適しています。
CT検査
放射線を用いて肝臓を含む腹部全体を詳細に観察します。
造影剤を使うことで血流の状態や腫瘍の広がり、転移の有無も判断可能です。
胃カメラ検査
肝硬変患者では胃や食道に静脈瘤が発生しやすく、内視鏡検査で食道から十二指腸までを観察し合併症の有無を調べます。
肝生検や腹腔鏡検査
必要に応じて肝臓組織を直接採取し、炎症や線維化の程度、原因を詳しく調べる侵襲的検査も行われます。
甲状腺ホルモンと肝機能障害の関係性
肝機能障害の原因は多岐にわたり、甲状腺の病気が肝機能に影響を与えている場合もあります。
甲状腺ホルモンの異常は肝臓の代謝や酵素活性に変化をもたらし、原因不明の肝機能異常として現れることがあります。
必要に応じて甲状腺ホルモン検査も行い、肝障害の根本原因を正確に特定することが重要です。
肝機能異常を発見したらどうすべきか

血液検査で肝機能異常が指摘された場合は、必ず医療機関で詳しい検査を受けてください。
症状がなくても肝臓のダメージが進行していることがあり、放置すると重篤な肝疾患に移行する恐れがあります。
早期に適切な診断と治療を受けることが、肝臓の健康維持と重症化予防につながります。








