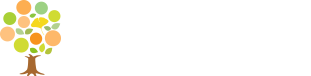- HOME>
- 肝機能障害とは?原因・主な疾患・治療方法・予防
肝機能障害とは

肝機能障害とは、簡単にいうと肝臓の細胞に何らかの障害が起こり、肝臓の本来の働きが低下した状態です。
肝臓は体内で重要な代謝や解毒機能を担う臓器であるため、障害が進行すると全身に影響を及ぼします。
初期には自覚症状が乏しいため、健康診断や人間ドックの血液検査で初めて異常が見つかることも多くあります。
肝機能障害の主な原因
肝機能障害の原因はさまざまで、複数の要因が絡み合って発症することもあります。
代表的な原因を以下に示し、それぞれについて詳しく説明します。
ウイルス性肝炎
ウイルス性肝炎は、ウイルスによる感染で肝細胞が炎症を起こす疾患です。
A型〜E型の5種類の肝炎ウイルスがあり、日本ではB型肝炎とC型肝炎が多く見られます。
これらは主に血液や体液を介して感染するため、血液製剤の使用や輸血、注射針の使い回し、ピアスや入れ墨による感染、母子感染などが主な経路です。
脂肪肝
脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態で、肝細胞の30%以上に脂肪が沈着すると診断されます。
アルコール性は過剰飲酒が原因で、非アルコール性は肥満や糖尿病、脂質異常症など生活習慣に起因します。
特に非アルコール性脂肪肝の一部は「NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)」と呼ばれ、進行すると肝硬変や肝がんのリスクがあります。
薬剤性肝障害
医療機関で処方される薬だけでなく、市販薬、漢方薬、サプリメントなどでも肝機能障害が起こることがあります。
特に抗生物質、解熱鎮痛剤、精神系薬剤、抗がん剤などは注意が必要です。
薬を開始した後に肝機能の異常が見られる場合は、医師に相談しましょう。
自己免疫性肝炎
免疫機能が誤って自身の肝細胞を攻撃することで生じる肝炎です。
中年以降の女性に多く、慢性的な経過をとることが一般的です。
原因ははっきりしていませんが、ホルモンバランスの変化や感染症、薬剤などが引き金となる可能性が示唆されています。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)
自己免疫反応によって肝内の小さな胆管が徐々に破壊され、胆汁がうっ滞することで肝細胞が障害される疾患です。
長期にわたり無症状で経過することが多いですが、進行すると肝硬変や肝不全に至る可能性があります。
ストレスの影響
精神的ストレスは交感神経を刺激し、肝臓の血流を減少させることにより肝機能を低下させるとされています。
過剰なストレスは心身両面に悪影響を与えるため、注意が必要です。
肝機能障害の症状
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれるほど、障害があっても初期には症状が出にくい臓器です。
そのため、血液検査で肝酵素(AST、ALT、γ-GTPなど)の異常が見つかっても、自覚症状がないことがほとんどです。
進行時の症状
進行すると、皮膚や白目が黄色くなる黄疸、倦怠感、吐き気、食欲低下、かゆみ、むくみなどが現れます。
さらに進行すると腹水の貯留や、アンモニアが脳に影響する「肝性脳症」を発症することもあります。
肝機能障害の検査と診断

肝機能障害の診断の第一歩は血液検査です。
血液を採取してAST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビンなどを調べ、肝細胞の炎症や胆汁うっ滞の有無を確認します。
必要に応じて、ウイルス検査、腹部エコー、CT、MRI、組織検査なども行います。
肝機能障害の治療法
肝機能障害は、自覚症状が現れにくいため気づかないまま進行してしまうことが多い病気です。
しかし、放置すると肝硬変や肝臓がんなど深刻な状態へと進展するリスクがあります。
だからこそ、早期発見と適切な治療、そして何より日々の生活習慣を見直した予防が非常に重要です。
肝炎ウイルスによる肝機能障害の治療法
急性の肝炎ウイルス感染では多くの場合、安静と補液などの対症療法で自然に治ることが多いです。
重症化した場合はステロイド治療を行うこともありますが、約1~2%の方は劇症肝炎となり急激に肝機能が低下し危険な状態になることがあるため注意が必要です。
慢性化したB型肝炎ではウイルスの完全排除は困難であるため、ウイルス量を抑える治療で病状の進行を防ぎます。
C型肝炎は抗ウイルス薬の進歩により、高確率でウイルス増殖を抑制できるようになりました。
アルコール性肝炎と非アルコール性脂肪性肝炎の対応
アルコール性肝炎では禁酒が絶対条件です。
必要に応じて抗酒剤(ALDH阻害剤)を用いる場合もあります。
一方、アルコールが原因でない脂肪肝炎は生活習慣の改善が治療の中心となり、肥満や糖尿病などの基礎疾患のコントロールも重要視されます。
薬剤性肝障害と自己免疫性肝炎の治療
薬剤やサプリメントが原因の場合は、これらの使用を中止することが第一です。
自己免疫性肝炎では免疫を抑える薬やステロイドを使い、炎症を抑制します。
症状の改善後も薬の管理は専門医の厳密なコントロールが必要で、勝手に中断すると悪化する恐れがあります。
肝硬変の重篤な合併症と対応
重度の肝硬変では、肝臓の解毒機能が低下し、血液中の有害物質が増加して肝性脳症を引き起こすことがあります。
肝性脳症は意識障害や昏睡を伴うこともあり、命に関わる深刻な状態です。
こうした症状が疑われる場合は速やかに医療機関での治療が必要となります。
肝硬変の進行を抑えることが治療の中心となり、生活習慣の改善や薬物療法で肝臓への負担を軽減します。
肝機能障害の予防とは

肝機能障害の予防は、主に肝炎ウイルスの感染防止と生活習慣の改善にあります。
肝炎ウイルスはA型からE型まであり、それぞれ感染経路が異なります。
B型やC型は主に血液を介して感染し、D型はまれです。A型とE型は糞便を介して感染します。
いずれも性交渉による感染リスクもあるため、性行為の際はコンドーム使用が推奨されます。
特にB型肝炎は体液を介して感染しやすいため、注意が必要です。
また、食生活の改善や適度な運動、禁煙、節酒など日常生活の見直しも肝機能を守るために非常に重要です。
健康診断で異常値が見つかった場合は放置せず、速やかに医療機関に相談して適切な検査と治療を受けるようにしましょう。
肝機能が低い方の生活習慣改善方法
肝機能障害の原因はさまざまですが、特に脂肪肝などの予防には生活習慣の改善が効果的です。
以下のポイントを日常に取り入れてみましょう。
バランスの良い食事を心がける
肝臓が正常に機能するためには、8種類の必須アミノ酸を含む良質なたんぱく質の摂取が必要です。
主食・主菜・副菜をそろえ、特に外食時は野菜や副菜をしっかり摂ることが肝機能維持に役立ちます。
高脂肪の食事を控え、適正なカロリー管理も忘れずに行いましょう。
ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取
肝機能が低下するとビタミンの蓄積能力も落ちます。
緑黄色野菜や海藻、きのこ類などビタミンやミネラルを多く含む食材を積極的に摂り、食物繊維によって糖や脂質の吸収を抑え、腸内環境を整えることが重要です。
良質なタンパク質を適切に摂る
肝臓の修復には魚介類、肉類、大豆製品、卵など良質なたんぱく質が必要です。
ただし加工肉は脂質や添加物が多いため摂取量に気をつけましょう。
休肝日を設ける
アルコールは肝臓に中性脂肪を蓄積させ、消化管の粘膜も傷つけます。
週に2日程度の休肝日を設け、1日おきに飲酒し休む習慣が望ましいです。
過度な飲酒は肝機能障害を悪化させるため節酒や禁酒を心がけましょう。
適度な運動の実践
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は非アルコール性脂肪肝の改善に効果的です。
また筋肉は肝臓の代謝機能を補助し、ストレス軽減にもつながります。
日常生活に無理なく運動を取り入れることをおすすめします。
肝機能障害予防の具体策
ウイルス性肝炎予防には、食べ物は十分加熱し、生ものの取り扱いに注意することが基本です。
性行為の際はコンドーム使用を徹底し、不特定多数との接触を避けることが感染リスク軽減につながります。
生活習慣面では、規則正しい食生活、適度な運動、適正なアルコール量の摂取、禁煙が肝臓の健康維持に効果的です。
飲酒の目安は、男性で1日40g以下、女性で20g以下とされており、ビール500mlやワイン2杯弱に相当します。
さらに、定期的に健康診断や人間ドックを受け、異常があれば速やかに医療機関を受診することが、肝機能障害の早期発見と治療につながります。