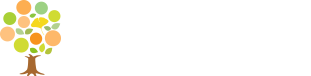- HOME>
- 院長紹介
いとせクリニックの診療方針
当院では、消化器疾患を中心に診療しています。消化器疾患とは簡単にいうと『おなかの病気』のことを指します。
その範囲は食道・胃・十二指腸・小腸・大腸といった食べ物の通り道である消化管から、肝臓・胆嚢・膵臓といった食べたものの消化に関わる臓器に及びます。
皆さんも一度は『お腹が痛い』『お腹の調子が悪い』という症状を経験したことがあると思います。たとえば『お腹が痛い』と思っても、それが胃なのか腸なのか、それともすい臓や肝臓といった別の臓器なのかは、一般にはなかなか分かるものではありません。はっきりとした痛みではなく、「なんとなくこのあたりに不快感がある、違和感がある」ということもあります。また、お通じの調子で生活の質が左右されることもあり、いろいろな病気が潜んでいる場合もあります。
当院ではそのようなお悩み・症状をお持ちの方をお待ちしています。まず詳しくお話を伺い診察し、必要に応じて内視鏡や超音波などの検査を行います。
- 消化器内視鏡学会専門医が長年の経験に基づき、苦痛の少ない胃や大腸の内視鏡検査を行っています。
- 肝臓学会専門医による肝臓を中心にした腹部超音波検査も行っています。
また、肝臓は人体内で最大の代謝臓器です。糖尿病・コレステロールの異常などの生活習慣病(いわゆるメタボ)も肝臓の働きと密接に関わっています。このため生活習慣病についても積極的に診断し、将来動脈硬化や心筋梗塞・脳卒中が起こらないよう予防に努めます。
そのほか、風邪や頭痛、高血圧などの内科一般の病気についても総合内科専門医である院長が診療しております。お気軽にご相談ください。
医師の紹介

糸瀬 一陽 (いとせ いちよう)
経歴
- 1997年大阪大学医学部卒業
- 1997年大阪大学医学部附属病院 第一内科 研修医
- 1998年国立大阪南病院(現・大阪南医療センター)消化器科
- 2002年大阪大学医学部附属病院 消化器内科 医員
- 2007年大阪大学大学院 医学系研究科 修了
- 2007年大阪大学医学部附属病院 消化器内科 医員
- 2009年関西労災病院 消化器内科
- 同部長を経て
- 2017年いとせクリニック開院
資格
- 内科学会総合内科専門医
- 消化器病学会専門医・指導医
- 消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 肝臓学会専門医
- 緩和ケア研修修了
- 日本医師会認定産業医
受賞
2007年度 AASLD Young Investigator Travel Award
アメリカ肝臓学会での発表において Young Investigator Travel Award を受賞いたしました。発表演題のタイトルは以下の通りです。
Involvement of regulatory T cell dynamics in the achievement of biochemical response in 48-week PEG-IFNα2b and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis C patients
2009年度 シェリング・プラウアワード
C型肝炎の臨床分野における卓越した研究として『Schering-Plough Award臨床分野優秀賞』を受賞いたしました。
受賞した論文はこちらです。
Enhanced ability of regulatory T cells in chronic hepatitis C patients with persistently normal alanine aminotransferase levels than those with active hepatitis.
その他
- 2018年度〜2023年度兵庫県立武庫之荘総合高校校医
ロゴマークに込めた想い

幸せな人生を送るための大切な要素の一つとして『健康』があります。
私たちの一生のうちには健康な時もあれば、そうでない時もあります。しかし医療技術は日々進歩しており、早期発見・早期治療により健康な日々を取り戻せる可能性がますます増えてきています。
患者さんの顔色が優れない時があっても一緒に治療に寄り添い、いつか温かい笑顔になっていただきたいという想いで診療しています。たわわに実った果実のように笑顔あふれるたくさんの患者さんをイメージし、ロゴマークに想いを込めました。
木全体でitoseの 『 i 』 を表しています。そして、木の実の中に一つだけ『いちょうの葉』があります。これには3つの意味を込めています。
- 当院は消化器内科を中心に診療しておりますので『胃腸』という意味。
- 医学を一から教え育てていただいた出身大学の校章が『銀杏(いちょう)』であるということ。
- もう一つの意味についてはこのホームページの中にヒントがありますので、答えは直接院長にお尋ねください。